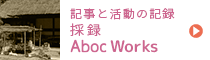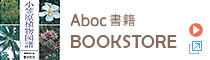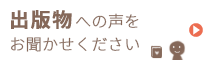スリランカ
スリランカは面積約65,600km2で、北海道より少し小さな島国である。インド亜大陸の南に添うように、北緯5度55分から9度55分に位置する。島の南西部は湿潤なモンスーンの影響により、海岸地区から高地まで雨量が多い(コロンボは約2,500mm、高地では3,000mm)。南東部から北西部にかけては、雨量が少なく、砂漠に近い乾燥地。北部は十月から一月の北東モンスーンで雨が多くなる。
人口は約1,600万人。紀元前五世紀頃、インドからシンハラ人が渡来し、先住のベッタ族を征服して王朝を開いた。仏教を取り入れた王朝は独特の宗教文化を造り上げ、現在に至っているが、紀元前二世紀頃よりインド南部のヒンズー教徒のタミル人が侵攻を繰り返し、言語、宗教の違う両者は未だ北部ジャフナ近郊において、紛争が絶えることがなく、実に二千二百年間あきもせず争っていたことになる。十六世紀以降はポルトガル、スペインが侵入したが、イギリスが一九世紀初め全土を征服し、植民地とした。第二次大戦後、民族意識の高まりの中、一九四八年二月、イギリス連邦の自治国セイロン、一九七二年には、国名をスリランカと改め、完全独立国となった。
一九九四年十月二十日。旧首都コロンボ着、十七時二十五分。成田を出発してから福岡経由約十時間半。現地時間は時差三時間半の遅れ、コロンボ(カトゥナーヤカ)国際空港は市内から北約30kmにあり、入国審査やら市内までの交通時間などで、宿泊ホテルのヒルトンに着いたのは薄暮の七時半頃であった。夕食後九時、室内から見るコロンボ港はすでに闇に閉ざされ、遠く港湾施設の点々とした明かりが見えるだけだった。
○古都キャンディ市
十月二十一日、午前九時出発。バスを仕立てて、北東に約120km、島の中央部にある古都キャンディ(カンデー)に向かう。道すがら広がる田園風景はヤシ林と水牛を除けば、全く日本の風景と変わらず、稲の育ちもよい。スリランカはサイクロン(台風)の襲来はなく、農産部は豊かで、米220万t、茶18万t、天然ゴム13.4万t、キャッサバ54万t、サツマイモ14万t、コプラ12万tが産出されている。ちなみに、農耕用水牛は全土に84万頭おり、ヤギ(49万頭)より多い(一九八一年統計)。
ココヤシはイギリス時代からのプランテーションがある。コプラを輸出するほか、果実はカレー料理や飲料として利用されている。ココヤシの繊維も輸出され、上得意は日本で、日本での輸入量はスリランカが85%を占めている。洗車ブラシ、たわし、ほうきなどに加工され、日本の車のピカピカなのも、家の掃除ができるのも、皆スリランカのおかげというわけである。業界で使われている「シュロ縄」のほとんどはスリランカ産のヤシ繊維で、昭和四十年代以降、日本のシュロ繊維生産の減少と生産コストの高騰から、原料は次第に海外依存になったわけで、シュロ縄は厳密にいえば、ココヤシ縄ということになる。
キャンディは標高300mほどの山々に囲まれた狭い盆地にあり、北で栄えたシンハラ王朝がインドからの侵入者に追われ、最後に王朝をかまえた場所で、イギリスに滅ぼされるまでの三百年にわたり、シンハラ文化が華開いたところである。その王宮の一部は現在、仏歯寺として利用され、小乗仏教のメッカとして参拝者が絶えることはない。年に一度の夏に行われるペラヘラ祭には世界中から人々が集まり、開期二週間のうちに文化のすべてが燃え、一気にその情熱が爆発するという。
現地でのホテルはキャンディ湖畔にあるホテル「スイス」である。植民地時代に建てられたもので、木造二階建てで白く塗られた外壁と長方形のガラス窓、褐色の屋根瓦はイギリス建築の特徴がよく出ている。中庭にはプールがあり、周囲には多くの花木が植栽され、なかでもキツネノマゴ科メガスケパスマ(Megaskepasma erythrochlamys)の花盛りで、赤い苞が一際鮮やかである。刈り込まれた芝生の縁に、イギリス時代に植えられたと思われるタマリンド(Tamarindus indica)の大木(推定樹齢二百年)があった。このマメ科植物は東南アジアからアフリカに分布しており、スリランカでは、シャンバラー(Siyambala)、中国では酸梅などと呼ばれ、若い豆果は野菜として、果肉は調味料や造酒などに利用される有用樹である。クロトン、コンロンカに混じって、珍しいところでは一見クワズイモかと思わせる、フィロデンドロン属では最大級の葉をもつPhilodendron giganteum、インドクワズイモの巨大な葉に白色斑が鮮やかなもの、肋骨状に深く切れ込んだ葉のAlocasia porteiなどがある。
キャンディ湖(一周約2.5km)に沿って、風致木が植えられ、大木から低木に至るまで現地名、学名の書かれているラベルがつけられているのには感心した。最も多い木はノウゼンカズラ科のタベブイヤ(Tabebuia rosea)で、この原生地は中米からコロンビアである。葉はホンコンカポックを一回り大きくしたような掌状葉、小葉は二から三枚、花はピンクである。英名はRosy trumpet treeで、これだけの大木が一斉に咲いたら、開花期はさぞかし見事であろう。つぎに多い大木はアメリカネム(Samanea saman)で、これは日立グループの宣伝で「この木何の木」の二代目としても有名だが、花は濃いピンクであっても遠目にはあまり目立たない存在である。
街はずれに家内工業的にパテック織りを作っている所に見学することになったが、筆者としてはあまり身につける物には興味がないのでパスさせてもらい、付近の山の植生を見ることとした。
山は高さ20mほどの照葉樹が茂り、林床との空間は刺をもった低木や蔓性植物で占有され、とても分け入ることは困難であり、道路沿いの切り通した崖から中を覗く程度で、林縁を構成する植物が観察の中心となった。林縁から密林の奥まで林床を覆いつくしているのはアグラオネマ(Aglaonema commutatum)で、茎が長く伸び、絡み合って、かなり暗い場所でも葉柄が詰まり葉がしっかりして、赤く熟した実は野生の逞しさを見せている。アグラオネマは熱帯アジアに約50種あるといわれ、観葉植物の中でも最も暗い所に強く、人工光の地下室でも水さえやっていれば、一年位では枯れることはない。外国ではインドア用の植物として利用度が高いが、日本ではそれ程は利用されていない。原因としては、低温に弱いことで、冬期10℃以下では越冬できないためである。
崖に真白い果実を先端につけ下垂しているのは、ヤコウカ(Cestrum nocturnum)である。この熱帯アメリカ原生のナス科植物は夜になると芳香を放ち、庭園樹、香料植物として、全世界に広がっている。ここにあるものはおそらく、鳥によって種子が運ばれたものであろう。すでに周囲の植生に同化して違和感はない。よく間違えるのは、この夜香花と夜来香(イエライシャン)で、それらは同一の物と思っている人が多い。往年の女優山口淑子(李香蘭)に歌われ、戦時中の大ヒット「夜来香」とともに青春を過ごした方々には懐かしい植物だが、歌で知っているだけで実際の植物を知る方はまずいないため、名も似ていて夜になると香りを放つことから取り違えられているのである。
元祖本家の「夜来香」はガガイモ科の蔓性植物で、華南地方が原生地。和名ウスイロカズラ(Telosma cordata)である。葉は対生し、葉身は広卵形から長楕円形で、長さ6.5から9.5cm、幅4から8cm、先端は尖っている。花は散形状集散花序で葉腋につき、多いものは30個ほどつく。花冠は黄緑色で五裂、多肉質である。花は薬用にされ、結膜炎に効く。また芳香油に利用され、今はアメリカ、ヨーロッパでも栽培されている。
ガガイモ科の植物は、ホヤ(サクララン属)が観葉植物として使われているが、マダガスカルジャスミン(Stephanotis floribunda)は芳香鉢物として人気がある。灌木類のコンロンカ(Mussaenda)、ヤエザキクサギ(Clerodendrum fragrans var. peniflorum)は薄いピンクの花を頂生につけ、顔を近づけると微かな芳香を放っている。民家には鳥の階状の白い花をつけているシロゴチョウ(Sesbania grandiflora)がエンジュに似た樹形を茂らせている。若枝や幹が緑で、葉が細かいことを除けば、エンジュと間違えるほど似ている。スリランカではカツルームルンガ(Katuru-murunga)と呼ばれ、東南アジアからオーストラリアに分布するマメ科の植物である。この木の用途は広く、若葉や若莢、花は野菜とされ、樹皮からはガム、葉、根から薬が採れるので、熱帯地方では民家に多く植えられている。
十月二十二日、キャンディ市の隣町のペラデニヤへ。植物園の南側に広がるキャンパスは面積10km2と世界一の敷地を有するペラデニヤ大学である。ゆったりとした環境の中、約4,000人の学生が学んでいる。医学、工学、法学、農学、文学の五つの学部があり、スリランカでは最古の大学で、入学は最もむずかしいといわれている名門校である。
○ペラデニヤ植物園
ペラデニヤ植物園の総面積は5.6km2である。一八二一年開設され、ジャワのボゴール植物園、シンガポール植物園と並び熱帯地域の三大植物園の一つである。植物の種類は4,800種、徒歩で丸一日見て回っても、到底見切れるものではない。
今回は日本大学教授の小山鐵夫博士の紹介状をもらっての訪問である。小山先生は、一九六九年から一九七九年まで、スミソニアン研究所とセイロン大学が協力して「セイロンのフロラ」をまとめるフロラ・プロジェクトの中心人物として活躍され、当時の助手であったスミトラアラッチ(Sumithraarachchi)氏は現在園長である。またジャヤスリヤ(Jayasuriya)氏は標本館館長になっている。植物園訪問については、昨日からガイドのロハンが連絡を取っているが、あいにく園長、館長とも公用で、コロンボに出張しているとのことであった。電話に出た職員が小山先生を存じているとかで、とにかく出張先に連絡をしてみるとの話であった。
正面受付でわれわれの訪問を告げると「園長は先程からお待ちです」との答え。察するところ、われわれのために急遽コロンボから戻られたに違いない。入口の右手奥に事務棟があり、その二階に園長室があった。小山先生のメッセージと日本酒の手土産を手渡し、訪問の目的を話し、挨拶が済むと一時間半ばかり、セイロンのフロラについて講義をして下さるとのことで、われわれとしても願ってもないことであった。このニュースを下で待つ仲間に告げ、園長を紹介した。
園長はかつてのインドのネール首相に風貌が似て、長身で気さくな人である。講義内容はペラデニヤ植物園の説明から入った。植物園は農業省の管轄で、後日行くハクガラ植物園やガルオヤ(Gal Oya)、ルフヌー(Ruhunu)、ウィルパットウ(Wilpattu)などの国立公園を総括し、種の保存や薬用、有用植物の研究、自然保護などを現在主な仕事としている。過去においては、有用植物の繁殖も大きな目的の一つであった。敷地はマハウェリ川の蛇行に囲まれた地にあり、大きく分けると園芸種、緑化庭園樹、野生種、ヤシおよび薬草のブロックなどに分けられて、入口には園芸学校もある。そのうちもともとここに自生する自然林は約22%あり、中央広場には日立グループ宣伝の「この木何の木」の初代の木ベンジャミンゴムノキがある、などの説明の後、標本館館長のジャヤスリヤ氏に交代、スリランカには3,300種の高等植物があり、850種が固有種で、まだまだ新種の発見もあるとのこと。最近ではインパチエンス(Impatiens)、エクサクム(Exacum)の新種が見つかったそうである。
ジャヤスリヤ氏はやや小柄で、日本人によく似た体形の人物である。生真面目な性格らしく、講義に見られるその順序だった話ぶりからもそれが感じられ、標本館の長としてはうってつけの人に思えた。話は英語であったが、「私は日本語が話せないので、英語で話します。皆さんにはゆっくり、はっきり話しますので、ご理解できると思います」との前置きがあった。
両氏は一九六九年、セイロン大学植物学科を卒業するとすぐセイロン・フロラのプロジェクトチームの小山先生の助手として採用され、今では農業省の高級役人で博士でもある。講義終了後有意義なお話しをして下さったお礼を述べ、さて全員は広大な植物園へとくり出すこととなった。
講堂は園芸種ブロックの一角にあり、一歩外は熱帯植物が溢れている。温室や寒冷紗ハウスが点在している広場の中央は、高さ20m以上のテンブス(Fagraea fragrans)が一本あり、樹形がピラミッド形で一見刈り込まれたように見えるが、周囲が開けた場所では、これが自然樹形ではないかと思われる。タイからスマトラ、フィリピンに分布するフジウツギ科の植物で、材は堅く、彫刻用材、家具、船、器、床板に使われ、葉、枝は薬用にされている。この木が多いのはシンガポールで、特にセントサ島の高木の三割位はこの木である。庭園樹として黄斑が目立つソング・オブ・インディア(Dracaena reflexa ‘Song of India’)は3mになり、頭が丸く、スタンド作りのように見える。現地ではプライド・オブ・インディア(インドの誇り)と呼び、原生地がインドであることから、こちらの名が元祖でソング・オブ・インディアの名のほうは誰かがアレンジして名づけたものと考えられる。同じ仲間で薄い中斑があるものをソング・オブ・ジャマイカと日本では言っているが、ジャマイカには原生していないことからこれもまた誰かの創作であろう。
園内を二分する形で、中央にはメイン・ストリートが走り、入口近くに香料植物園がある。その中の一角にニクズク(Myristica fragrans)が40から50本植えられている。
○香辛料の歴史
ニクズク科の植物はアフリカ、インド-マレーシア、太平洋諸島に約120種あり、ニクズクが代表種でマルク(旧称モルッカ)諸島が原生地である。高さ10から20mになる常緑高木、果実は径3から9cmの球形で、中心より縦に裂開し、種子は真紅の仮種皮に包まれている。
この仮種子はメースと呼ばれ、スパイス、薬用として珍重され、その高価さは世界一といわれている。種子はナツメグといい、肉の料理には最上のスパイスとされ、菓子の中でも、ドーナツ作りには不可欠のものとされている。成分はミリチシン、ピネン、オイゲノール、サフロールなどでその気品の高い香りが貴ばれている。薬用としては、消化不良、腹痛、下痢、媚薬として漢方で用い、日本では、苦味健胃薬に配合されている。
十世紀頃、原生地のマルク諸島はアラビア人と船による貿易が始まり、海のシルクロードを通り、アラビアからは陸路、ラクダ隊商によってヨーロッパ玄関ロイスタンブールに運ばれ、食肉文化圏の国々に売られてきた。この高価なスパイスはバスコ・ダ・ガマの喜望峰回りのインド洋海路が発見(一四九八年)された後は、西欧列強の利益独占の争いとなった。十六世紀にはポルトガル、十七世紀にはオランダと貿易権は移っていたのである。十八世紀からはフランス、イギリスによって植民地に移植され、各地で栽培されるようになった。今ではインドネシア、東アフリカ、西インド諸島が主産地となっている。
フトモモ科のチョウジ(Syzygium aromaticum)も、やはりマルク諸島が原生地で、ニューギニアまで分布している。英名のクローブは、蕾の形が釘(clou)の形をしていることから、同様に丁子の丁は釘の形の意味から名づけられたものである。これも十七世紀まではマルク諸島の特産で、ここからヨーロッパ、中国に運ばれた。中国では、紀元前三世紀すでに宮廷料理や薬用として用いられていた。中国経由で日本に当時運ばれてきたものは正倉院御物として現在でも保存されている。
チョウジは香辛料として利用される他に、古来より第一級の媚薬として用いられ、中世アラビアでは不老の薬として、毎日食べれば白髪にならないといわれてきた。風邪、咳、虫歯、眼病、胃痛、肝臓の薬として、特に防腐、殺菌力は香辛料の中では一番とされ、食肉文化圏では、肉の保存に欠かせなかった。
エジプトではピラミッドやスフィンクスが建造されたころより、高貴な人物が死去するとミイラを作った。死は魂が体を一時離れた現象であり、また必ずもどってくると信じられ、その時自分の体が腐乱していたり、消滅していたりすると、魂は行き場がなくなり、永久にこの世とあの世をさまよわなければならないと思われていたからである。
ミイラ作りは、最初は簡単に乾燥させていたが、次第に死体をさらに腐らないように内臓諸器官を取り出し、ニクズクやチョウジといった香辛料を詰め込んだ。形が崩れないように包帯でグルグル巻きにして、よく乾燥(これらの地はほうっといても乾燥する)させるとミイラができ上がる。
よく「ミイラ採りがミイラになる」との格言があるが、この言葉をついでに解説すると、何百年も経たミイラはこれらの香辛料が全体に浸み込み、ミイラ自体が貴重な香辛料のカタマリとなるわけで、一体掘り当てて漢方薬屋、香辛料屋に持って行くと莫大なお金となりうる。ロールスロイスを買って、家を建ててもおつりがくるくらいの価値があったそうである。そんなわけで欲の深い一発屋が競って、近世までミイラを探し、あまりの欲で目がくらみ、出口がわからなくなって、自分自身も干物になったということである。現在でも博打などに手を出して干物にされた話があり、人間欲のある限り、この格言は生き続けることであろう。
○この木何の木
Great Lawn(芝生広場)は、よく刈り込まれた芝生が広大に拡がる小さなゴルフ場顔負けの空間で、なだらかな起伏の低地部にかの有名な日立グループの宣伝に登場した初代「この木何の木」が鎮座している。現地ではジャワ・フィグと呼ばれているが、要するにベンジャミンゴムノキ(Ficus benjamina)である。
この巨木の枝張り面積は約1,600m2(約500坪)、主幹は目通り約6m、巨大な大蛇を思わせる枝が無数に放射され、先端は地面に着くのを防ぐため、竹の支柱で支えられている。立て看板の説明では樹齢約百年ということだが、高温多湿の熱帯では驚くほど成長は早い。成長の過程において周囲に競合する物がないために、傘状に広がった樹形はベンジャミンゴムノキの成木の樹形の標本というべきか。疵陰樹としての標本としての役割もあり、強烈な太陽を避けて、数十人の若者や学生が集まっている。ここは敬度な仏教徒の国で独身の男女の交際もつつましく、個々の特定カップル行動はつつしまれ、昨今の日本のような見苦しいカップルはいない。
ナンヨウスギの仲間(Araucaria columnaris)が並木となっている道(Cook's pine Avenue)が川沿いに続いている。ナンヨウスギの仲間はかつてクック船長が初めてヨーロッパに紹介したもので、この仲間の総称としてクック・パインと今でも呼ぶことがある。最初にノーフォーク島で採集された末商が現在神奈川県藤沢市江ノ島植物園に数本あり、20mほどの大木に育っている。路地植えでこれ程の大木になるのはおそらくここが北限であろう。一見の価値はある。
並木からはずれて高さ30m以上あろうか、ナンヨウスギ科のカウリコーパルノキ、すなわちカウリマツ(Agathis australis)が、ギリシア建築のエンタシス状の巨大な樹幹で天を突いている。別名ナギモドキとあるように、葉はナギの葉に酷似している。ニュージーランド、ニューカレドニアが原生地で、大きいものは高さ40m近くなり、幹は直径6mに達する。材は緻密で樹脂が多く、木工材、船材などに、地中に永く埋もれた倒木は化石樹脂となり、コハクの代用として珍重されている。
○世界最大の種子
この大木の日陰には世界最大の種子で名高いオオミヤシの樹が並木として植えられている。別名フタゴヤシ、ウミヤシともいい、セーシェル諸島のプララン(Praslin)島、キュリューズ(Curieuse)島の固有種である。フランス人が最初モルディブの海岸でこの種子を拾い、永いこと原生地がモルディブであると思われ、学名もLodoicea maldivicaとなり、モルディブ産を意味する名が付けられた経緯がある。また、最初に拾ったフランス人は原植物が解らず、海から来たヤシという意味で「ココ・ドゥ・メール」、つまりウミヤシと名づけたわけである。
このヤシは雌雄異株で完全な成木になるのに百年以上を要し、果実は受粉して8から10年で熟すといわれ、核は二個の楕円体が連結した形をしており、好色的置物として珍重されたりしているが、現地では器としても利用されている。種子の周囲は90cm、重さ30kgに達し、一個の種子としては最大でギネスブックにも載っている。ここでは雌雄交互に植えられ、雌株は多い物では十数個の実をつけている。果実は一つの木で大小があり、年ごとに成ったものでも大きさが変わる。
一個ずつ番号が打たれているのは、盗難除けというわけでなく、おそらく受粉した年月や成長の度合いを調べるための研究標示となっているのであろう。付近には赤花のパキラ、黄花のビワモドキ(Dillenia suffruticosa)、藪状に繁ったピンクのサンタンカの仲間(Ixora lobbii var. stenophylla)がある。これは一般に売られているイクソラ・キネンシス(サンタンカ)やイクソラ・コッキネアと異なり、花数が多くなく、お茶の葉形の葉は長い節間につき、ラフな感じで、よほど気をつけて見なければ、何となく通り過ぎてしまう物である。
植物園は一八二一年開設され、何しろ174年の歴史(訪問当時)があるので当時植えられたものは成木になり、植物本来の姿になっている。われわれは日頃観葉植物として鉢植え物を取り扱っているが、そのほとんどは幼態形の姿を見ているに過ぎない。これが大人の本来の姿と思っていたら、大きな間違いである。
先月もわたし達の仲間でもあり、先輩である東海農園の吉田幸夫さんによると、氏が主幹となっている園芸雑誌に載っているフィクス・プミラ(オオイタビFicus pumila)を図鑑で見ると、まったく異なる植物に思われるとの読者の質問があったという。われわれが通常吊鉢などで見ているこの植物はすべて幼態形で、葉もちぢれて小さく枝も細い。成木になると葉は長さ5から10cmになり、革質でバリバリ、径3から5cmのイチジクを成らせ、まったく異なる形態となるのである。
園内メイン・ストリートのほぼ中央部には、直径500mほどのグレート・サークルと呼ばれるロータリーがある。よく手入れされた芝生が広がっていて、それを突っ切ると当植物園の看板ともいうべき、大王ヤシの並木道が続く。
大王ヤシ(Royal Palm)を別名キャベツヤシともいうのは、中南米でこの新芽を野菜として利用してきたことによる。日本国内でも輸入されたカンヅメが売られており、筆者も食したが、水煮の筍の歯ざわりはあるが、少々堅くてあまり美味ではなかった。
道の右奥は深く、シナノキ科、アオイ科、アオギリ科、ウルシ科、ムクロジ科のコレクションがあるが、時間の関係上パスさせてもらい、左側にあるクワ科のイチジク属のコレクションに移ることとする。
数十種ある中で何といっても、圧巻はベンガルボダイジュ(Ficus benghalensis)の板根である。普通この仲間は、気根が多く出るのが特徴である。ここにあるものは、気根が皆無で幹のシバ付けより蛇かタチウオのような板根で地表を覆っている。個体差によっても多少の変異があると思われるが、老木になると次第に気根が消滅していくのかもしれない。または通るのに邪魔とか何らかの人為的なことで気根が切り取られたのかもしれない。
ベンガルボダイジュは高さ30mになり、インドでは聖樹の一つとされ、小さなイチジクは食用、樹液はトリモチとして利用されている。
植物園の一番奥はマハウェリ川で行き止まりとなり、蛇行した川に沿って左右に道は分かれている。マハウェリ川は、源流は最高峰のピドゥルタラガラ山(標高2,524m)に発し、東北部のトリンコマリー湾に注いでいるスリランカ一の大河である。
さて午後も三時を過ぎるころになると、先程からの怪しい雲行きからポツポツ雨が降りだしたと思いきや、大粒のスコールとなり、池畔にある四阿で雨宿りを余儀なくされた。現地の中学生20人程の先客があり、声をかけると最初ははにかんでいた態度であったが、だんだん打ち解け、カメラを始め、われわれの持ち物に興味を示し、ワーワーと、とんだ国際親善となった。
池の端にクワズイモによく似たサトイモ科の植物で、マダガスカル原生のティフォノドルム(Typhonodorum lindleyanum)が数十株の群落を作っている。クワズイモと異なる形態としては、葉がやや細長く、葉柄が短く、また芋の部分が1.5m以上垂直に立ち上がることである。
クワズイモは芋の太さに応じて多少は立ち上がるが、その重さに耐えることはできず、原生状態では地面に芋がのたうつ形で生えている。われわれが通常鉢物として取り扱っているものは適当な長さで切られ、無理に立てられた姿であって、植物生態の本来の姿ではない。
スコールに濡れて、先端をしな垂れている大きな竹は、世界最大の竹として有名なウォラ(Dendrocalamus giganteus)である。インドのアッサム地方からミャンマー、タイに分布しており、高さ20から30m、桿径が30cmになり、輪切りしたものは洗面器などの容器として使われているほか、材は土木建築用材、家具などの材料にされ、堅牢である。
タケ類は世界に47属1,250種あるといわれ、そのうち日本には12属662種あり、実に世界の半数以上を占めている。
日本の竹を一躍有名にしたのは、アメリカの発明王エジソンが電球を作り、フィラメントに京都、嵯峨野の竹を黒焼きにして使い、最初に電球に明かりを灯したことである。筍も関西では嵯峨野の竹が一番とされている。
関東では戦前までは東京、目黒の筍が有名であった。黒ボク土壌が深いことも条件であるが、良い筍を作るには秋に根を掘り起こし、深さ約1mの溝に堆肥や肥料と一緒に埋め戻して管理すれば、季節になると太くて柔らかい筍ができるというわけである。このような舌の上でとろけるような上等な筍は庶民の口には入りにくい。
東南アジアを旅すると巨大な筍を野菜として売っていることを目にすることができる。もちろんウォラやパイトン(Dendrocalamus asper)などの筍である。日本に輸入されているラーメンの具としてお馴染みのメンマは、中国南部、タイ、ミャンマー、フィリピン、台湾に分布しているマチク(D. latiflorus)で、これも高さが20mになり、成竹は建築現場の足場などにも利用されている。
一見柳楊と見られる大木はシダレイトスギ(Cupressus funebris)で、小枝は下垂して遠目ではまったく柳であるが、小枝に密生する葉は三角卵形状で確かに針葉樹である。この木は中国揚子江流域に多く、この樹形の奇異さから庭園木として利用されている。
イトスギ属(Cupressus)はヒノキ科の常緑高木で温帯から亜熱帯に約12種あり、中でも園芸鉢物として人気の高い園芸品種のゴールドクレストは、コニファーの中でも淡い緑と円錐形が好まれている。野生種はカリフォルニアのモントレー付近に原生するモントレーイトスギ(C. macrocarpa)で、幼木はわれわれが通常見ている円錐形をしているが、成木になると水平方向にも枝が開張し、まったく異なる樹形となる。園芸界では円錐形の樹形の針葉樹をコニファーと呼んでいるが、さにあらずコニファーは球果植物の意味で、球果(毬果)とは木化した鱗片葉が集まって球形あるいは楕円体となったものである。裸子植物のスギ、ヒノキ、ビャクシンなどの球果がその例で、広い意味では針葉樹類は一般に球果をつけるのでこれらの植物の総称というわけである。
○高地ヌーワラ・エーリア
十月二十三日、イギリス植民地時代の面影を残す避暑地ヌーワラ・エーリアに向かう。キャンディからバスで約三時間の行程、海抜2,000mの高原に街がある。
1,500m位から茶畑が広がり、耕して天に上る段々畑は山麓から山頂に至る。途中思わぬ交通事故で道路が二時間にわたってストップ、山間を通る細道ではバスがすれ違うのもやっとの状態で、事故車が道を塞ぎ、警察の検証が済むのを待つしかない。
スリランカの茶栽培は、十九世紀末に原生林を切り開いたイギリス人の大農園に端を発するもので、当初低地から始まり次第に高地まで広がった。現在の茶栽培面積は約24万ha、生産量は一九七一年の約22万tをピークに減少傾向にある。加えて国際価格の低迷や最大の産出国インドや東アフリカなどの新興産地の輸出増加で、輸出額は伸び悩んでいる。生産の減少している原因は樹の老齢化と不十分な施肥管理といわれているが、一九七一年末からの国有化以降公営企業による官僚的経営も足を引っ張っているようだ。
紅茶の他、三大農産物に数えられるゴム、ココナツ生産は二十世紀に入ってからである。ゴム園は海抜650m以下のウェットゾーンにあり、作付け面積は茶よりわずかに少なく約20万km、ココナツは小規模経営が多く全栽培面積の30%である。紅茶は高地で栽培された物が良質とされ、低地ほど品質が落ち、それぞれの葉のブレンドは現在二つの公社が行なっている。
事故処理が終わりやっと九十九折の山道が開通した。業を煮やして歩き始めた連中を約1km先で拾って、さらに高地へと進む。見渡す限り全山茶畑、もちろん通路際までというより茶畑の中を車が走っている感じである。チャを見ると樹高1m程度で、人力で摘むのによい高さになっている。幹は太い物で人間の腕位になっており、八十から百年の歳月が感じられる。老樹は効率が悪いため若樹と植え替えられて、廃棄処分にされる。これらは根張り枝ぶりがすばらしく、盆栽に仕立ててヨーロッパにでも売り出せばとも思うが、何とももったいないことである。チャは移植に弱く、余程前もって根回しをやらなければ活着はむずかしく、現地ではその技術はないかもしれない。
○茶の歴史
チャ(Camellia sinensis)は中国南部が原生地で、雲南には樹齢千年を超え、高さ10m以上のものが何本もあるといわれている。中国伝説中の帝王「神農」は薬の神、農業の神、火の神、易の神として祭られているが、一日に何種類かの植物を噛み分け、薬になる物を選別して、夕方になるとチャの葉を噛んで草の毒を消したといわれている。チャは薬草の元祖のようなもので、ミャンマー北部のカチン族は、頭痛がするとチャの葉を食べ、切り傷に葉を当てて治療するといい、現代でも口臭除去、消化不良、便秘、鎮静などの効果が喫茶を習慣づけている。
日本では真言宗の開祖空海(七七四~八三五年)が入唐して恵果に学び、八〇六年(大同一年)帰朝した時にチャの種子を持ち帰ったのが初めとされているが、これは栽培に失敗し育たなかった。鎌倉時代になり、臨済宗の開祖、栄西(一一一四~一二一五年)が二度にわたり入宋し、著『喫茶養生記』の中に宋からチャの種子を持ち帰り、博多の聖福寺にて栽培に成功したことが記されている。その後京都宇治付近、静岡川根付近などに、栄西の弟子達によって移植されたのである。以後高価な飲み物として特権階級の人々に飲まれてきた。童歌に「ズイズイズッコロバシゴマミソズイ茶壺に追われてトッピンシャン」は、将軍に献上するためのお茶壺道中を歌ったもので、お触れが出て、二、三日前から街道を掃き清め、そそうのないよう行列が通り過ぎるまで戸を閉めて家の中に子供達を閉じ込めておき、「ヌケターラドンドコショ」、すなわち通過して遠くに行ったら緊張もとけ、子供達も外に出され、喜んでいる様子を歌ったものである。江戸時代中期になると、商人が客に対する接待として用いられるほどになったが、まだまだ生産量は少なく、一般庶民の口には入らなかった。明治維新後、大井川、天竜川などに橋が架けられ、多くの川人足(約800人)は職を失い、政府は失業対策事業として茶の栽培を奨励し、現在静岡茶生産日本一となったわけである。
茶の製法は大別すると、葉を発酵させる(紅茶)、させない(緑茶)に分けられ、酵素を利用して発酵させ、途中の半発酵で作るのが烏龍茶、緑茶は蒸製と釜炒り製に分けられ、日本茶は蒸製不発酵茶で、この製法は雲南省南部のタイ系民族に起源をもつといわれている。現在この技術をもって茶を製するのは日本だけであり、その日本茶はビタミンの含有が一番多い。
俗説では紅茶の起源は大航海時代にあるという。極東にきた南蛮船は長い航海で新鮮野菜が不足し、特にビタミンC不足で壊血病にかかる船員が多く、中国に寄港した際ビタミンCを含んだ釜炒り茶を購入して、この病気の予防に役立てようとした。しかし熱帯、高湿度のインド洋で船倉に積んだ茶は発酵し、本国に戻るころは白い粉を吹いたものに変身。どうしたものか、高価なお茶は捨てきれず、天日で乾かして飲んでみたもののカビ臭く今一味も悪い。砂糖、スコッチウィスキーなどを加えだましだまし飲んだ。一応いけるということで、単に偶発的産物で紅茶ができたわけである。今では、紅茶は貴族の飲み物などと気取っているが、「何てことはない、腐ったお茶の捨て損ない」が紅茶なのである。
○ハクガラ植物園
先程の交通事故で紅茶工場、農園見学はお流れになり、イギリス植民地時代に建てられた木造三階建てのグランドホテルに到着したのは午後一時半も少し回ったころとなった。遅めの昼食をとり、ペラデニヤ植物園の分園といわれるハクガラ植物園に行く。この植物園(面積約2.2km2)は2,000mの高地にあり、世界各国から集められた温帯系の植物が植えられている。日本から持ち込まれたビャクシン(Juniperus chinensis)やスギ(Cryptomeria japonica)の目通り8から9mの大木が数本ある。これ程の樹は原生地日本でも数は少ない。
この植物園の開設は、もともとマラリアの特効薬キニーネの原料となるボリビアキナノキ(Cinchona ledgeriana)を栽培するのが主要目的であった。アカネ科キナ属はアンデスを中心に約40種があり、そのうち数種がキニーネが採れる樹として栽培されている。
古くインカの時代から熱病の特効薬として樹皮をQuina-Quinaと呼んでいた。ヨーロッパでは十七世紀にはすでにその効用が知られ、スペイン総督夫人のマラリアを治療して以来有名になり人気も沸騰した。次第に天然物の減少で、価格が上がり、また乱伐で絶滅の危機にもさらされて、十九世紀になり各国の植民地で増殖が行われたのである。一八五四年、オランダではジャワで移植に成功し、インド、ビルマ(現ミャンマー)、セイロン(現スリランカ)、後に日本統治時代の台湾などで栽培された。キニーネ、シンコニン、キニジンなどの各種のアルカロイドを含み、なかでも毒性はキニーネが最も強く、これは原形質毒で直接細胞に作用し、少量で機能を高め、多量だと死に至るものである。
高さ5mほどの斑入りのイヌマキが数本ある。剪定した枝が樹下に転がっていたので小枝をいただいてきた。帰国後温室に約30本挿木してみたが、時期が十月下旬であったので活着率は悪かったが、翌年の六月現在、四本の発根が見られた。淡黄色不規則な覆輪であまりきれいではないが、珍しいものである。
園内の低木で新葉が白い綿毛に包まれた一極目立つ物があった。キツネノマゴ科の植物らしいが、稲穂状に付く花はブルー、名称の表示はなく、正体不明の植物である。
ホテルに戻り、夕食まで多少の時間があったので街を散策した。街といってもニューバザール・ストリート沿いに約300m、商店や市場が並んでいる小さな田舎町で、町並みに比べ、何処から出てきたのかやたら人間が多く、商売も繁盛しているようだ。山間の町なので鮮魚は少ないが、干魚、高原野菜は種類も多く、日用雑貨、洋品なども豊富である。ここでは本場のカレー粉を土産として買った。
スリランカでは各家庭ごとにカレーを作り、その家の味があるのだが、毎度たくさんの材料を砕き、カレー粉を作る時間がない人のためにベースとしてのカレー粉が売られている。トウガラシ、カルダモン、コショウ、シナモン、ウコン、ココヤシなどが主原料で熱を通して煎ってあるものと、生の二種あり、500gが100円位と滅法安いのも土産として魅力的である。
スリランカといえば、カレーのほかに宝石が昔から有名でヌーワラ・エーリアから東南約60km、ラトナプラは採掘が盛んな街である。
紀元前十世紀、ソロモン王はシバの女王にセイロン島産のルビーを贈り、その心を射止めたといわれ、『アラビアン・ナイト』では、シンドバットがラトナプラ(ラトナは宝石、プラは街の意味)を訪れ、十三世紀中国からの帰りにマルコ・ポーロは『東方見聞録』の中でセイロン島の宝石について書いている。近年ではチャールズ皇太子がダイアナ妃に婚約指輪として贈ったのがスリランカ産の最高のブルーサファイアであった。スリランカではダイヤモンド以外の宝石何でも産出するといい、代表的なものはアレキサンドライト、キャッツアイ、サファイア、ルビー、ムーンストーンなどで、世界の宝石商は10回や20回訪島しなければ、一丁前の宝石屋とはいえないという。
十月二十四日、朝食前にホテル付近の植生見学、高地のためか朝霧が深い。周りは小さな畑が多く、レタス、ニンジン、ネギ、サトイモ、キャベツなどが栽培されている。畑を仕切る生垣はわれわれが初めて目にする植物が多く、シソ科で3から4mになる木本植物は紫の花穂が長さ30cm、葉をもむとシソの香りがした。
ヤマモガシ科の樹木で羽状葉、互生単葉の両方をもつものがあった。日本ではカイヅカイブキの剪定を深目にやるとスギの葉状になることがあるが、剪定した跡もなく、どうも不可解な現象であった。藪に鮮やかな薄いピンクの花を咲かせている蔓性植物があった。トケイソウの仲間のPassiflora novo-guineensisでニューギニア島の原生種である。日本でわれわれが見ているトケイソウは紫とグリーンの混ざった花で決して美しいとはいえないが、この種は真紅の花のベニバナトケイソウにも劣らない品格がある。何とか種子が手に入らないかと藪を見渡したところ黄色に熟れたウインナーソーセージ大の果実が二個あるのが確認された。刺の多い蔓など避けながら木に登り二個確保。一個は完熟、中には数十個の種子が入っていた。これは同行した観葉植物の作り屋、愛知の山本明和園さんに預けることとした。そのうち生産出荷となれば、必ず人気ナンバーワンになることは間違いなしである。
○戒厳令
朝食後八時三十分、今日はインド洋に面したリゾート地デヒワラ・マウント・ラビニアに下る予定で皆ロビーに集合した。ところが添乗員川嵜氏より足止めの報告が入る。それは昨夜コロンボでスリランカ大統領選に備えて野党第一党、統一国民党が集会を開いている最中に爆弾テロがあり、候補者のガミニ・ディサナヤケ氏を含め約50人が爆死、約300人が負傷し、大統領は全土に「非常事態」を宣言し外出禁止令が出たためであった。コロンボ市内は戒厳令が敷かれたという。アクシデントである。仕方なくロビーホールで様子を見ることとなった。
新聞発表では、LTTE(タミル・イーラム解放のトラ)の犯行疑いが強いということであったが定かでない。事件の記事がこれまたすごいもので、頭部や足がふっ飛ばされて転がっている被害者、即死した犬などを一面に大きな現場写真で報道している。日本では到底発表できぬ写真である。
格好をつけて、うやうやしくウェイターが持ってくる紅茶を飲みながら、他にやることもない。嫌気がさすころ所轄の警察署の許可が出て、二時間遅れの出発となった。道すがら散在する家屋から小村落まで弔意を表す白旗が掲げられ、公用車以外の車は走っていない。街はふだん人間でごった返して、車はその間を抜けるありさまなのが、無人の広野を走るがごときであった。
茶畑が切れるころ、小休止。ガイドのロハンを呼び、この辺にはクジャクヤシ(Caryota urens)から採れる黒砂糖を作っている農家があるはずで、案内を乞いたいと言うと「どうしてそんな事まで知っているのか?」と言いつつ、道際の家まで連れて行ってくれて、値段の交渉までやってくれた。半球形のかたまり1kgが80円程度で、とにかく安い。八個も買い込んだ。サトウキビで作られたものは石灰を入れて固まらせるので独特な味がするが、このカリオタ黒砂糖は花柄から出る液を釜で煮つめただけの物で、多少外気に当てると溶けやすいが、コーヒー、紅茶あるいは煮物用に便利で美味である。
実はこの村に黒砂糖がある話は数ヶ月前に来られた大田市場FAJ情報企画室の長岡求さんからの情報があったからである。
ヘアピンカーブの下り坂が続く道端に、少年がドライバーや観光客相手に花束を売っている。通り過ぎるとカーブに再び花束を売る少年が立って、何度かその姿を目撃した。しかもその少年が同一人物であることに気がついた。何と少年はわれわれが行き過ぎると急斜面(落差50m位)を直線に下り、われわれより早く次のカーブに到着しているのだった。五度目にはこの健脚と情熱に打たれ車はストップ、花は要らないけれど10ルピーを進呈した。ガイドの話では少年と同じ仲間が5から6人おり、家計の手助けとして働いているとのことで、登り下りで走る距離は一日数十kmになるという。
戒厳令が発令されているコロンボ市内には入れず迂回をする。辻々には陸軍兵士が銃を持ち、重々しい空気があたりを支配している。われわれは外国人観光客ということで検問されることはなかったが、それでも通行証の提示を求められたのは二回あった。道がすいていたこともあって、予定通りマウント・ラビニア・ホテルに着いた。
白亜のホテルはコロニアルな雰囲気で、かつて英国の文豪サマーセット・モームがこのホテルに逗留し文筆活動をしたという。モームはわれわれが大学受験の時、彼の短編小説『雨』『月と六ペンス』などの一節から英語の試験が出題され、文学的中身はさておき、思い出の多い作家である。
さて、この夜のディナーでは、ホテルに無事着けた安堵感と同時に緊張が緩んだ空腹感からか、みな争うようにして食べていた。お決まりのスパイス、香料の効いた料理にワインは文明社会の象徴か。さらに大形イセエビともいうべきロブスター(ウミザリガニ)に舌鼓を打った。
ところで翌朝は、疲れがどっと出たばかりか、昨夜のあたりかまわずの暴飲暴食が災いして、体調を崩したものが続出するさわぎとなった。
十月二十五日、強行軍とアクシデントで体調を崩した仲間は薬を飲み、今日一日はホテルで安静。彼らを残して海岸の道、ゴールロードを南下、ベントタに向かう。途中ココヤシ酒を作る村があり、植林された丈の高いココヤシに何本ものロープが網の目のように張り廻らされ、採取人がそのロープを伝い、花柄からしたたる樹液を集めている。集められたものは、20リットルほどの容器に移され、工場に運ばれる。ここのヤシ酒は南洋諸島で作られている自然発酵酒ではなく、蒸留酒で、アルコール度も40度を超えるものがある。
ベントタの一つ手前の街アルトガマは漁村。街道筋でコンパネ上に並べてカツオ、サワラ、大きいサメのブツ切りが売られているが、この熱帯の炎天下で冷蔵設備もない状態では到底刺身などにできない。ホテルで出る料理も仕入れは、おおむねこのような場所からくるので要注意である。
ベントタ・ビーチ・ホテルで昼食。周辺にあるのはモモタマナ、テリハボク、タコノキの仲間、ココヤシなどの海浜性植物で目新しいものはない。
十月二十六日、二十時四十五分発のエアーランカUL四五六便に搭乗。盛りだくさんの思い出の地、スリランカを離れる。かつてアラビア人が海を越え、東の地との交易を行ない「海のシルクロード」の中継地として栄えた「インド洋の真珠の涙」スリランカ。またあらためて訪れたい島の一つである。
- 初出掲載紙:(社)日本インドア・グリーン協会発行『グリーン・ニュース』
- スリランカ植生誌No.1(グリーン・ニュース、一九九五年五月号)
- スリランカ植生誌No.2(グリーン・ニュース、一九九五年八月号)
- スリランカ植生誌No.3(グリーン・ニュース、一九九五年九月号)
『熱帯植物巡礼』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
書籍詳細
-
完売
[2000/03/25]田中耕次 著 / アボック社 / 2000年 / B6判 286頁
定価1,650円(本体1,500+税)/ ISBN4-900358-51-7
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』